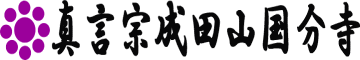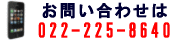法要法事のお布施
真言宗成田山国分寺の法要法事の仙台お布施
四十九日の法要法事
四十九日法要法事になります。「忌明け」「四十九日」「満中陰」法要法事ともいいます。四十九日は中陰と呼ばれるこの世とあの世の中間の世界を漂っていた故人の魂がどこに行けるか最後の審判が下される日です。その忌明けが「満中陰」です。ようやくあの世での生を受けるとされています。その為、四十九日に法要法事をするとされ、僧侶や近親者を招いて、盛大に供養します。この日に中陰壇は片付けます。中陰壇に
百か日の法要法事
「
百か日の法要法事
「
一周忌の法要法事のお布施
死後一年の一周忌は亡くなられた翌年、三回忌は二年後、七回忌は六年後。その後十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、五十回忌とけじめとなる縁者が集まり故人を偲ぶ回忌法事です。その始まりとなるのが一周忌法要法事です。
- 2階白木祭壇・本堂祭壇等で行う法要法事(参列者35名まで)・・・2万5千円
- 同法要後会食等で別室使用したり別途会場設営が必要な場合・・・3万円5千円
一周忌や三回忌などの大切な法要法事を省略することはできませんが、都合によっては回忌を営めないこともあります。そのときは、早めに菩提寺に連絡し、法要法事を依頼します。家族は、仏壇にお供えものをして、ふだんよりもていねいに供養します。
開眼供養
開眼供養のお布施 2万5千円※成田山以外の場所へ出向く場合は別途料金が決まっております。
開眼供養とは新しい仏像、仏画、仏壇、墓などの完成の際に営まれる法要のことです。
納骨法要法事
納骨法要 お布施4万円/4万5千円※成田山以外の場所へ出向く場合は別途料金が決まっております。納骨を行う式に当たります。
故人の近親者、親しい友人、知人などごく内輪で納骨を行います。一般的に忌明けの四十九日をかねて納骨法要法事をすることが多いようです。
位牌開眼
お布施 7千円(合同)⁄2万5千円(個別)
新しくお位牌を作られた時は、開眼をします。開眼、入仏、お
追善供養会
お布施4千円(1霊位)/追善塔婆にて供養
夏のお盆は8月15日を中心に、迎え盆、送り盆といいます。春彼岸は春分の日を中心に前後を含んだ一週間です。 真言宗成田山国分寺では、お盆の8月15日ごろ、春彼岸の3月20日ごろ1年1度の特別合同追善供養会を行います。
お盆の読経供養 三十三回忌
お布施29万7千円/毎年8月13日午前11時30分開式
※お布施は9千円×33枚塔婆×33回忌分の供養となります。
毎年、夏のお盆に行う特別な供養です。申込時、塔婆に申込者名、供養日、故人名、戒名、命日、家族からの供養の言葉を記していただき、三十三回忌までの塔婆33枚建立します。通常のお盆の供養は1年後にお焚き上げしますが、こちらは、申込時33枚の塔婆を通年供養し、三十三回忌まで供養を重ねます。それにより1枚あたり33回供養を行い、33枚の塔婆と33年供養を合わせると1089回にもなる大変特別な供養になります。
十三仏の供養読経 三十三回忌
お布施7万8千円/毎月第1日曜日午前11時30分開式
※お布施は6千円×十三仏分、33年分の塔婆預かりを含みます。
十三仏とは、初七日忌から三十三回忌までのそれぞれの回忌の仏の総称で、故人は、回忌ごとにそれぞれの仏のもとを巡り、諸仏諸菩薩の功徳を頂きます。この供養を行うことで、諸仏諸菩薩は故人を通し、生前近しかった人たちも見守り福徳を施してくださいます。
初七日忌:不動明王 二七日忌:釈迦如来 三七日忌:文殊菩薩
四七日忌:普賢菩薩 五七日忌:地蔵菩薩 六七日忌:弥勒菩薩
七七日忌:薬師如来 百か日忌:観音菩薩 一周忌 :勢至菩薩
三回忌:阿弥陀如来 七回忌:アシュク如来 十三回忌:大日如来
三十三回忌:虚空蔵菩薩
はじめに、護摩供養塔婆を十三仏の13枚準備します。それに施主名、供養日、故人名、戒名を記し、十三仏の福徳を入れます。そのうえで、十三仏の定められた年/月により、護摩で十三仏の供養読経を行います。その際、縁者を代表して、施主の名前を読み上げ、護摩供養塔婆をお焚き上げします。
そのほかの法要法事
法要法事で使用する人数・会場によってお布施が違います。お布施はご家族の法要法事に合わせてください。
仙台お布施に関するお問合せは下記にて承ります。
真言宗成田山国分寺住所 :〒980-0845
宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉33–2
電話番号 :(022)225–8640
FAX :(022)225–8655