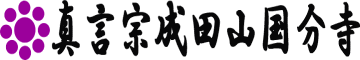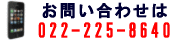お布施の説明
真言宗成田山国分寺のお布施の説明
真言宗成田山国分寺の仙台お布施説明会
お布施に関する説明会は毎週土・日曜日11:30から納骨堂、永代供養墓の説明と一緒にこなっております。(予約は不要です。正月準備期間の12月中旬〜正月期間中の2月3日迄を除きます。)
- 受付・・疑問や、不安に思われていることなどを真言宗成田山国分寺の成田山会館1階の受付にてお知らせ下さい。
- 説明会・・お布施について、また一般的なお布施の相場についても一通り説明させていただきます。
- 見学会・・当寺の法要会場、本堂など実際に見学していただきます。
- 質問、回答・・受付でお布施などの質問事項などにお答えします。
- 個別説明・・ほかの人と一緒では質問しにくい内容やプライバシーに関わる内容の場合には個別説明をご利用下さい。
葬儀、告別式が終了すると、埋葬、法要とお願いしなければなりませんが、臨終の立ち会いや枕経などから告別式までを一区切りとして、いったんお礼をします。このお礼のことを「お布施」といいます。布施は仏教用語で大乗仏教の五行に述べられています。五行は大乗仏教の要旨を簡潔に述べている大乗起信論に説かれています。布施は仏教における五行(菩薩の五つの修行・・布施、持戒、
またお布施は3種類あり、
- 財施・・・金銭や物を施す。
- 法施・・・仏の教えを説く。人のために読経する。
無畏施 ・・・恐怖や不安を取り除き安らぎを与える。
 つぎは財施であるお布施の金額について述べます。お布施の金額は人それぞれの価値観で決まるといわれますが漠然としていて、よくわかからないものです。お布施の金額に規定があるのなら、それにしたがいますが、規定がなく、よくわからないときは、日ごろのつきあい程度や、喪家の格を考慮しながら葬儀社や、お寺に「お布施の金額はいくらですか?」という直接的な聞き方でなく、間接的に「普通みなさんお布施はどのくらいにされていますか?」と相談して決められるのがよいでしょう。真言宗成田山国分寺のお布施はわかりやすく明瞭になっております。
つぎは財施であるお布施の金額について述べます。お布施の金額は人それぞれの価値観で決まるといわれますが漠然としていて、よくわかからないものです。お布施の金額に規定があるのなら、それにしたがいますが、規定がなく、よくわからないときは、日ごろのつきあい程度や、喪家の格を考慮しながら葬儀社や、お寺に「お布施の金額はいくらですか?」という直接的な聞き方でなく、間接的に「普通みなさんお布施はどのくらいにされていますか?」と相談して決められるのがよいでしょう。真言宗成田山国分寺のお布施はわかりやすく明瞭になっております。
お寺への謝礼、本尊へのお供えにあたる仏式のお布施は、半紙で中包みにして奉書紙で包むのが正式で、のし袋はつかいません。表書きは「御経料」か「御布施」「お布施」とします。表書き下段には喪家名か喪主名にします。薄い墨ではなく濃い黒墨で書きます。
会場が自宅やその他の会館などの場合は「お車代」、精進おとしや法事の会食を僧侶が辞退された場合は「御膳料」を包みます。「お車代」「御膳料」の袋は郵便番号欄などのない二重になっていない白封筒をつかいます。「お車代」「御膳料」は、通常のお布施と一括にして「御経料」「御布施」「お布施」とすることもあります。
お布施は僧侶に直接手渡しせずに盆にのせて、お礼の言葉をそえて丁重に渡します。
のし紙に表書きをして丁重に贈答をするのは、他に類を見ない、日本特有の習慣です。
もっと古いしきたりでは、贈り物には必ず目録を別に書き、添えて贈ったのですが、時代とともに簡略化され、金品の包みに、直接、贈答の目的を書くようになりました。
表書きのルーツは目録なのです。
お布施についての説明会
医師から臨終を告げられた時には、気が動転して、時間的、精神的に、ゆっくりと検討する余裕が無いものです。特に、お布施についての相場などは分からないものです。結果的に満足できないとか後悔が残ることもあります。葬儀をする際は、そうしたことがなければよいと思います。
葬儀においては、後々嫌な思いをしたくないものです。お布施などの相場を前もって知っておくことも必要です。
真言宗成田山国分寺の事前相談、お布施についての説明会などは残された家族と故人のためにあります。それが後悔しないための第一歩だと思います。さしあたって必要はないが、お布施の相場と知識を知りたい方もおられると思います。そのようなときは、合同説明会にお越し下さい。真言宗成田山国分寺のお布施の相場や一般的な知識を述べさせていただきます。
仙台お布施に関するお問合せは下記にて承ります。
真言宗成田山国分寺住所 :〒980-0845
宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉33–2
電話番号 :(022)225–8640
FAX :(022)225–8655